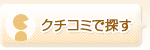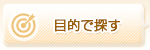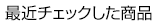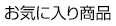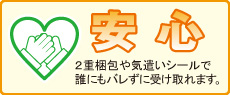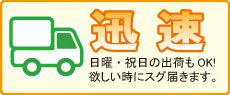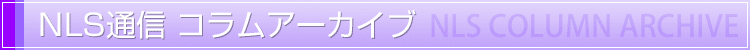
■Vol.206 (2023年07月配信)
LGBTに対する社会環境の変化と
最高裁の判断
7月上旬。経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場にある女子トイレの使用を制限されていることに対し国を訴えた裁判で、最高裁判所は「トイレの使用制限を設けた国の対応は違法」とする判決を言い渡しました。
性的マイノリティの人たちの職場環境に関する訴訟で、最高裁が判断を示したのはこれが初めて。
今後はさまざまな職場において、適切な対応が求められることになりそうです。
50代MTF男性による職場への訴訟
訴訟を起こしていたのは、50代のMTF。医師から性同一性障害と診断されており、性適合手術こそ行っていませんが、定期的に女性ホルモンの投与を受け、普段から女性として社会生活を送っています。
そんな彼女に対し、職場の上司は“他の職員への配慮”を理由に女子トイレの使用を制限。彼女が働くフロアから2階以上離れたトイレしか使用を認めませんでした。
限定的な状況ながら原告が逆転勝訴
この裁判は1審(東京地裁)が原告側の勝訴、2審(東京高裁)では敗訴となり、最高裁の判断が注目されていましたが、「許可された女子トイレを長年使用していても、トラブルは生じていない」「女子トイレの使用に明確に反対している職員はいない」などの理由から原告側の主張が認められました。
ただし、今回の判決は利用者が限定された“職場のトイレ”に関する判断です。トイレを含めた不特定多数の人々が利用する公共施設の使用のあり方は、改めて慎重に議論されるべきで、状況が変わればまた異なる判断が示される可能性もあるでしょう。
LGBT理解増進法案がチラつく背景
じつはこの判決の約1カ月前。衆議院では「LGBT理解増進法案」が可決され、性的マイノリティ当事者たちから悲痛な声が上がっていました。
この法案の大きな問題点は、可決直前に加えられた「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」という一文です。
これによって政府はLGBTに関する取組みに制限をかけることができ、つねに多数派にも配慮することで、結果的にLGBT当事者に対する差別を増進してしまうリスクを含んでいるのです。
そして…今回の裁判も職場が“他の職員への配慮”を理由に、LGBTの職員に過剰な負荷を掛けたことが要因ですから、多数派への配慮というものが、いかにLGBT当事者を苦しめるかが浮き彫りになったことでしょう。
みんなが共生できる社会を目指そう
最高裁の判断は、背景にあるこうした問題点を正しく掬い取った結果だと思います。しかし、今後また、同じような構図で同じような裁判が起こる可能性は大きく、それらを助長しかねないのが「LGBT理解増進法案」ともいわれています。
ただ…一方でマジョリティ側にいる人々は、少数派のためにこれまでの暮らしが変わるのがイヤだという方もいるでしょう。おそらく、すべての人々が納得する正解などは存在せず、どこかで誰かに負荷が掛かるのは仕方ないことなのかもしれません。
日本は世界に比べてLGBTに対する理解が遅れている国ですが、こうした裁判の判例や成立した関連法案の問題点を共有・議論することで、少しでも早く社会全体が成熟してくれるといいな…と願っています。
10人中、6人の方が、参考になったと評価しています。